 日本酒に関する記事
日本酒に関する記事 お酒の隠れた立役者「珪藻土」って?
お酒造りに欠かせないものとして知られる「珪藻土」。名前は聞いたことがあっても、実際どんなものか知らない方も多いのではないでしょうか? 珪藻土は、太古の植物プランクトン(珪藻)が化石化してできた土です。珪藻の殻は非常に細かい穴が無数に空いた構造をしているため、珪藻土は優れた吸水性・保湿性・断熱性を持ちます。この特徴を活かして、お酒の濾過や、建材、バスマットなど、私たちの身の回りで幅広く活用されているのです。
 日本酒に関する記事
日本酒に関する記事  製造工程に関する記事
製造工程に関する記事  日本酒に関する記事
日本酒に関する記事  その他
その他  日本酒に関する記事
日本酒に関する記事 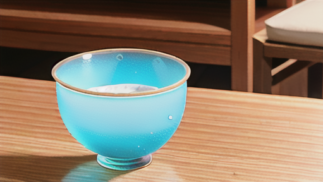 日本酒に関する記事
日本酒に関する記事  原材料に関する記事
原材料に関する記事  日本酒に関する記事
日本酒に関する記事  その他
その他  日本酒に関する記事
日本酒に関する記事  ビールに関する記事
ビールに関する記事  原材料に関する記事
原材料に関する記事  その他
その他  その他
その他  お酒の種類に関する記事
お酒の種類に関する記事  日本酒に関する記事
日本酒に関する記事  製造工程に関する記事
製造工程に関する記事  製造工程に関する記事
製造工程に関する記事  製造工程に関する記事
製造工程に関する記事